PROGRAM
専門コース(基礎/応用)
全国スクールリーダー育成研修 E.FORUM2025
2025.8.19(火) 〜 2025.8.20(水)
人文・哲学- 日時
- 2025.8.19(火) 〜 2025.8.20(水)
- 全国スクールリーダー育成研修 E.FORUM2025
- 会場
- 対面京都大学総合研究棟3・4号館
- 受講料(税込)
- 2日間 15,000円1日目11,000円、2日目4,000円
- 定員
- 席数を増加しましたので、定員になり次第申込終了
学校・教育委員会の関係者、教員志望の学生に限ります。

- 講師:西岡 加名恵
- 京都大学大学院教育学研究科 教授
専門は教育方法学(カリキュラム論・教育評価論)です。各学校において、どのようにカリキュラム改善を進めることができるのかに関心を持っています。本研修が、全国の先生方の有意義な交流の場ともなることを願っています。
【主な著書】
『教科と総合に活かすポートフォリオ評価法』(単著、図書文化、2003年)、『教科と総合学習のカリキュラム設計』(単著、図書文化、2016年)、『教科の「深い学び」を実現するパフォーマンス評価』(共編著、日本標準、2019年)、『「『生きる』教育」で変わる未来』(共編著、日本標準、2025年)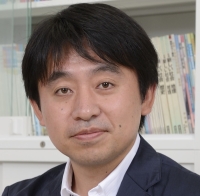
- 講師:石井 英真
- 京都大学大学院教育学研究科 准教授
【メッセージ】
学校で育成すべき資質・能力の中身をモデル化するとともに、それに基づくカリキュラム、授業、評価のあり方について理論的・実践的に研究しています。本研修が、それぞれの学校の授業改善を支え励ますものになることを願っています。
【主な著書】
『再増補版・現代アメリカにおける学力形成論の展開―スタンダードに基づくカリキュラムの設計』(単著、東信堂、2020年)、『授業づくりの深め方』(単著、ミネルヴァ書房、2020年)、『中学校・高等学校 授業が変わる学習評価深化論』(単著、図書文化、2022年)、『教育「変革」の時代の羅針盤』(単著、教育出版、2024年)など
- 講師:開沼 太郎
- 京都大学大学院教育学研究科 准教授
【メッセージ】
専門は教育行政(政策)学、教育工学です。教育におけるICT活用の方策とともに、教員の力量向上のための養成・採用・研修のあり方についても関心を持っています。皆様方と意見交流ができることを楽しみにしています。
【主な著書】
『世界と日本の事例で考える学校教育×ICT』(共著、明治図書、2023年)、『教育法規スタートアップ・ネクスト ver.2.0 Crossmedia Edition』(共編著、昭和堂、2023年)、『「教育の情報化」政策-ICT教育の整備・普及・活用』(単著、昭和堂、2024年)
- 講師:梅村 高太郎
- 京都大学大学院教育学研究科 准教授
専門は臨床心理学(思春期の心理療法)です。臨床心理士・公認心理師として、教育相談機関や精神科クリニックで、主に学校年代やそこを超えた青年期のカウンセリングに携わってきました。本研修が、コミュニケーションについて振り返る一助となることを願っています。
【主な著書】
『思春期男子の心理療法——身体化と主体の確立』(単著、創元社、2014年)、『京大心理臨床シリーズ13 事例研究から学ぶ心理臨床』(共編著、創元社、2020年)
- 講師:松下 佳代
- 京都大学大学院教育学研究科 教授
専門は、教育方法学、大学教育学です(特に、能力論、学習論、評価論)。主に、大学や中学校・高校をフィールドにして、研究と実践支援を行っています。対話型論証をぜひご自身のレパートリーに加えていただけると嬉しいです。
【主な著書】
『パフォーマンス評価 』 (単著、日本標準、2007年)、『ディープ・アクティブラーニング』(編著、勁草書房、2015年)、『 対話型論証による学びのデザイン 』(単著、勁草書房、2021 年)、『 測りすぎの時代の学習評価論』(単著、勁草書房、2025 年)

- 講師:奥村 好美
- 京都大学大学院教育学研究科 准教授
専門は教育方法学です。日本・オランダをフィールドに、教育評価や授業・カリキュラムのあり方について研究してきました。 本研修が、先生方が教育のあり方を見つめ直し、編み直していく一助となりますことを願っております。
【主な著書】
『<教育の自由>と学校評価 』 (単著、京都大学学術出版会、2016 年)、『 「逆向き設計」実践ガイドブック 』 (共編著、日本標準、2020 年)、『 変動する総合・探究学習 』(共著、大修館書店、2023 年)
- 講師:田口 真奈
- 京都大学大学院教育学研究科 准教授
専門は教育工学、大学教育学です。大学教員のICT活用や、大学におけるeラーニングの調査研究、大学の若手研究者が大学教員になっていくプロセスについての研究などを行っています。変化する大学教育の「今」をお伝えすることで、子どもたちの学びの場の「ちょっと先」を考えるきっかけになればと思っています。
【主な著書】
『模索されるeラーニング―事例と調査データにみる大学の未来』(共編著、東信堂, 2005年)、『授業研究と教育工学』(共編著、ミネルヴァ書房, 2012年)、『未来の大学教員を育てる―京大文学部・プレFDの挑戦』(共編著、 勁草書房, 2013年)、『教育工学における大学教育研究』(共編著、 ミネルヴァ書房, 2020年)
◇8月19日(火)9:30-17:30
【分科会A】パフォーマンス評価を活かしたカリキュラム改善
講師:西岡 加名恵 京都大学大学院教育学研究科 教授
各学校には、多様な子どもたちに対して、包摂性の高い、魅力的で効果的なカリキュラムを提供すること、そのためにカリキュラム・マネジメントに取り組むことが求められています。本セッションでは、各学校でカリキュラム改善を進めるために、パフォーマンス評価をどのように活用できるのかについて提案します。教科におけるパフォーマンス課題づくりのミニ演習を体験いただくとともに、ポートフォリオ評価法の進め方について解説します。「『生きる』教育」についても紹介します。
【分科会B】授業づくりの深め方
講師:石井 英真 京都大学大学院教育学研究科 准教授
繰り返される改革の中で授業づくりの軸がぶれたり、若手教師への授業づくりの基本的な技や考え方の伝承に困難を感じたりしてはいないでしょうか。本セッションでは、授業づくりの不易を確認し、「主体的・対話的で深い学び」「個別最適な学び」等をどう捉えるかについて考えます。そして、授業デザインの「5つのツボ」を紹介しつつ、授業づくりにおける基本的な考え方やポイントについて、ミニ演習を交えつつ学びます。その際、「教科する(do a subject)」授業をキーワードに、授業づくりの今後の方向性についても説明します。
【分科会C】「教育の情報化」のあり方を考える――GIGAスクール構想第2期の展望
講師:開沼 太郎 京都大学大学院教育学研究科 准教授
Society5.0の到来に伴って社会に求められる人材像の転換が迫られ、ICT 教育にまつわる政策は新たな展開を迎えつつあります。その中核として推進された「GIGA スクール」構想は、コロナ禍の影響によるオンライン教育の需要拡大を受けて1人1台端末環境の推進が図られ、GIGAスクール構想加速化基金を活用した端末更新等の新たな整備が進められつつあります。本分科会では、「教育の情報化」政策の特徴や課題について、過去・現在・未来の視点からICT 教育政策における課題について検討を行い、今後の「教育の情報化」のあり方を展望したいと思います。
【分科会D】関係性を育むコミュニケーション——聴く力と伝える力
講師:梅村 高太郎 京都大学大学院教育学研究科 准教授
多忙な教育現場において、生徒、保護者、そして同僚とのコミュニケーションは、教育活動を進める上で非常に重要でありながら、難しさや悩みを伴うことも少なくないかと思います。本分科会では、あらゆる人間関係の基盤となり、教育現場でのさまざまな課題解決にもつながる「聴く力」と「伝える力」について扱います。相手の心に寄り添い、その意図や感情を深く理解する「聴く力」。そして、自分の考えや気持ちを、相手を尊重しつつ表現する「伝える力」。これらのスキルについて、ミニレクチャーと体験ワークを通して理解を深めます。生徒や保護者との間に信頼関係を築き、同僚とのより良い協働関係を育むためのヒントを提供できればと思います。
【講演会】対話型論証による学びのデザイン―教科と総合での探究をどうすすめるか―
講師:松下 佳代 京都大学大学院教育学研究科 教授
不確実性、複雑性の増すこの時代、学校で身に付けてほしい力を一つ選ぶとすれば、私は対話型論証の力と答えます。これは小学校から大学までいろいろな授業を見る中で得た自分なりの答えです。ある問題に対して、他者と対話しながら、根拠をもって主張を組み立て、結論を導くこと、それが「対話型論証」です。私は小・中・高・大の先生方と、この対話型論証の実践と理論を創ってきました。この講演では、小学校・中学校・高校での事例をもとに、対話型論証のモデルや指導法を提案していきます。教科や総合学習での探究の指導のヒントになればと願っています。
※終了後、懇親会 18:00~20:00 開催あり(参加費要、ご希望の方のみ)
申込は8月5日(火)正午をもって締め切りました。
◇8月20日(水)9:30-11:30
【分科会E】個別化・個性化教育の考え方―オランダのイエナプランとダルトンプランを手がかりに
講師:奥村 好美 京都大学大学院教育学研究科 准教授
中央教育審議会答申「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して」などをきっかけに、多様な学習者を包摂することを目指して、「個別最適な学び」や「個に応じた指導」といったキーワードに注目が集まっています。そうした中、オランダのイエナプラン教育やダルトンプラン教育といったオルタナティブ教育も近年関心を集めています。本セッションでは、この二つの教育の考え方や具体的な実践を手がかりに、個別化・個性化教育のあり方やそこで求められる教師の指導性を考えてみたいと思います。
【分科会F】ICT活用は何のため?〜コロナ禍で変わる大学教育の現場から
講師:田口 真奈 京都大学大学院教育学研究科 准教授
ICT活用は何のために行うのでしょうか。日本では、大学教育におけるICT活用はコロナ禍前まではあまり進まず、eラーニングも限定的にしか広がっていませんでした。しかし、コロナ禍をきっかけにじわじわと変化がみられつつあります。MOOCをはじめとするオープンコンテンツの活用が広がる一方、対面授業の良さも改めて浮き彫りになっています。本セッションでは、大学教育の現場から見えるICT活用の変化をふまえ、これからの子どもたちが生きる社会を見据えて、学びのあり方について考えてみたいと思います。
SIP関連ワークショップ「真正で探究的な学びを実現するパフォーマンス課題とは」(無料イベント)
申込は7月25日(金)をもって締め切りました。
ワークショップ申込フォーム
ワークショップの詳細につきましてはこちらからご覧ください。
ワークショップ詳細
【共催】
京都大学大学院教育学研究科 教育実践コラボレーション・センター
京大オリジナル株式会社
■スケジュール
◇8月19日(火)
9:00~9:30 受付
9:30~9:45 オープニング
10:00~12:30 【分科会A】パフォーマンス評価を活かしたカリキュラム改善 西岡 加名恵 教授
【分科会B】授業づくりの深め方 石井 英真 准教授
12:30~14:00 昼休み
14:00~15:30 【分科会C】「教育の情報化」のあり方を考える――GIGAスクール構想第2期の展望 開沼 太郎 准教授
【分科会D】関係性を育むコミュニケーション——聴く力と伝える力 梅村 高太郎 准教授
15:45~15:50 研究科長挨拶
15:50~17:30 【講演会】 対話型論証による学びのデザイン―教科と総合での探究をどうすすめるか 松下 佳代教授
18:00~20:00 【懇親会】(軽食・ドリンク付き)
◇8月20日(水)
9:00~9:30 受付
9:30~9:45 オープニング
10:00~11:30 【分科会E】個別化・個性化教育の考え方―オランダのイエナプランとダルトンプランを手がかりに
奥村 好美 准教授
【分科会F】ICT活用は何のため?〜コロナ禍で変わる大学教育の現場から 田口 真奈 准教授
11:30~13:00 昼休み
13:00~16:00 SIP関連ワークショップ「真正で探究的な学びを実現するためパフォーマンス課題とは」(無料イベント)
