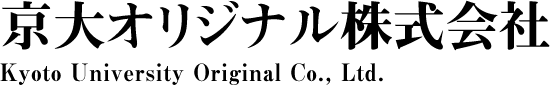ニュース内容
2025-07-10(木)
「AIを活用した、持続可能な地球社会に向けての政策提言」に協力
京都大学と日立製作所の共同研究により、AIを活用した地球社会の未来シミュレーションと政策提言に関する新たな成果が発表されました。2万通りのシナリオ分析を通じて、持続可能な望ましい未来に向かうか否かの分岐が2034年頃までに訪れる可能性が示され、早期の国際的対応の重要性が明らかとなりました。なお、本研究には京大オリジナル株式会社もデータ収集等で協力しております。
気候変動、生態系の劣化、経済格差の拡大、社会の分断、頻発する紛争など、地球社会は複合的な危機に直面しています。人類が安全に活動を続けるための地球的限界「プラネタリー・バウンダリー」(※1)に関する議論も進み、将来に向けた持続可能な社会の構築は、国際的な喫緊の課題とされています。その実現に向け、科学的根拠に基づいた未来予測と政策立案が今、強く求められています。
2017年、京都大学の広井 良典 教授(現:名誉教授)と日立製作所の日立未来課題探索共同研究部門(日立京大ラボ)は、AIを活用した未来シミュレーションと政策提言に関する技術(政策提言AIまたは未来シナリオシミュレーター)を共同開発し、自治体などで活用が進められてきました。今回の取り組みは、その技術を地球全体の課題に応用した「グローバル版」と位置づけられます。
今回の研究では、地球社会の現状と将来に関わる294の指標を国際機関等のデータから抽出し、因果関係に基づいたモデルを構築。その上で、AIを用いた「未来シナリオシミュレーター」により、2050年までの2万通りの未来を定量的に分析しました。
分析の結果、地球社会は7つの異なるシナリオへと分岐する可能性があることが明らかになりました。なかでも、「地域分散・成熟シナリオ」と「グリーン成長・協調シナリオ」は、環境・経済・社会の各側面において良好なパフォーマンスを示す未来像として注目されます。これらと、それ以外の回避すべきシナリオを分ける鍵は2034年頃までにあり、早急な対応が求められる結果となりました。特に前者は地域レベルでの経済循環や持続可能性をグローバルレベルへと積み上げていく対応、後者は国際的な協調行動、すなわち「ソーシャル・キャピタル」(※3)の強化が求められます。
コンピューターシミュレーションを用いた未来予測には、先駆的な研究として、1972年にローマ・クラブが公表し、地球資源の有限性を警告した『成長の限界』があります。ただし、当時は主に資源とエネルギーが焦点であり、気候変動、経済格差、ウェルビーイング(※2)といった現代の課題に包括的に対応する新たな手法の必要性が指摘されてきました。本研究は、『成長の限界』の問題提起を継承しつつ、AI技術を活用して、多元的かつ現代的な諸要因を視野に収めた内容となっています。今後は、データ収集やモデル構築に関する課題の改善が予定されています。
本研究は、AI技術を用いて地球規模の様々な課題を定量的に分析し、実行可能な政策を導く取り組みの重要性を示しています。特に2034年頃までの対応が未来の方向性を左右するという分析結果は、各国政府や国際機関にとって有用な指針となることが期待されます。
本研究は、京都大学人と社会の未来研究院『社会的共通資本と未来寄附研究部門』(2025 年 4 月より京都大学成長戦略本部 Beyond 2050 社会的共通資本研究部門)における研究成果となり、弊社ソリューションデザイン部 部長の川村健太が京都大学成長戦略本部 Beyond 2050 社会的共通資本研究部門の非常勤研究員として兼務しています。
【用語解説】
(※1)プラネタリー・バウンダリー:人類が安全に活動できる地球環境の限界値を示す概念。
(※2)ウェルビーイング:身体的・精神的・社会的に満たされた良好な状態。幸福や健康を含む。
(※3)ソーシャル・キャピタル:信頼関係や協力行動を促進する社会的なつながりや規範。
【より詳しい内容】
プレスリリース「AIを活用した、持続可能な地球社会に向けての政策提言~未来シナリオシミュレーターによる分析と展望~」https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000164782.html